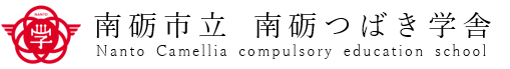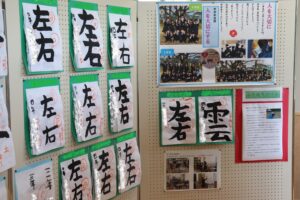カテゴリー: 3年生
5月30日(木) 自学の時間スタート
5月28日(火)2~6年生 つばき学習
5月27日(月) 意欲的に授業に取り組む3・4年生
5月23日(木) 自学の時間 全校オリエンテーション
来週から「自学の時間」が始まります。今日は、5限に全校オリエンテーションを行いました。
〇「自学の時間」のねらいは、できるようになりたいことやしたいことを自分で決めて、進んで活動することです。「自学の時間」は、学校で自分がやってみたいことを一人でする時間です。
〇活動してみたいことを自分で決めます。何をするか自分で決めることが、とても大切です。ただし、できることは、学校で安全にできる活動です。
他にも、活動場所や予定時間数、振り返りカードの記入の仕方と発表、相談等について、説明を聞きました。
「○○のしくみについて、○○を使って調べたい」、「折り紙で○○の作品を作りたい」、「ゴルフがうまくなりたい」等々、子供たちがどんな活動を考えてきてくれるか、とても楽しみです。



5月23日(木) さつまいもの苗植え
5月22日(水)花の苗植え




全校の子供たちでピロティで花の苗植えを行いました。環境美化委員会の担当の子供たちが、培養土を一輪車で運んだり、空きプランターを48個揃えたりして5限目に備えました。




8つのチームに分かれている子供たちは、上学年と下学年がペアになって活動しました。下の子の花選びを上の子が見守ったり、花を手際よく植えられるように上の子が下の子を優しくフォローしたりする温かい光景が見受けられ、大変ほほえましく感じました。




特に、今回は「じょうろで水をかける役」と「プランター側面の穴から水が出るのを確認する役」に分かれ、意識して水をあげることに心がけたので、花たちにたっぷりと水をあげることができました。明日からは、つばきの鉢と共にプランターの水やりも朝の日課になります。
5月18日(土) 運動会
「広げよう笑顔の輪」のテーマのもと、令和6年度の運動会が行われました。子供たちはこれまでの練習の成果を発揮しようと、一つ一つの競技に全力で取り組んでいました。一番遅くなってもあきらめずにゴールに向かう姿、そしてその子を応援する姿がとても印象的でした。また、運動会がスムーズに進むよう、競技や係の仕事を互いに確認したり、下級生に対して優しく教えたりする上級生の姿がたくさん見られました。特に、時間をかけて準備・練習をしてきた応援合戦では、1~9年生全員が団結して取り組むことができ、達成感や喜びに満ちた笑顔の輪がグラウンドいっぱいに広がりました。ご来場の皆様、たくさんのご声援をいただき、ありがとうございました。